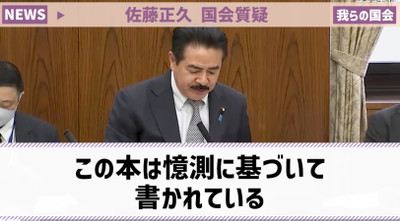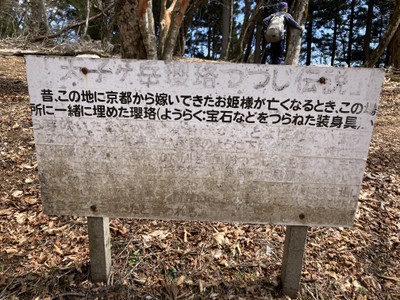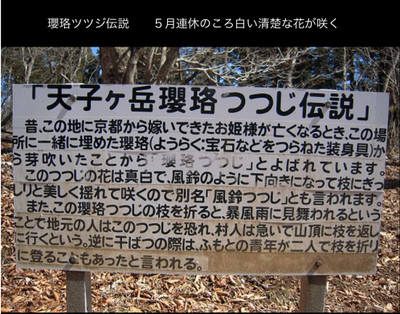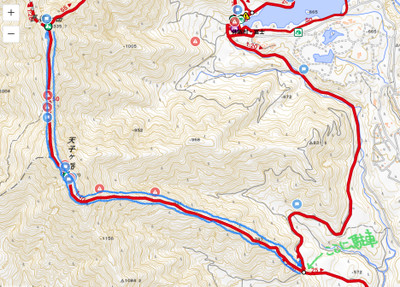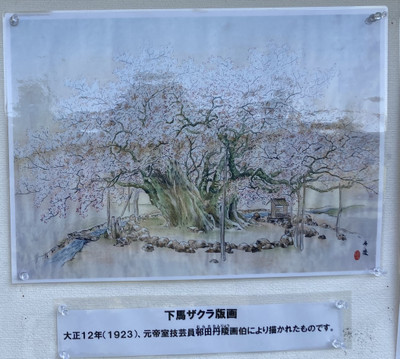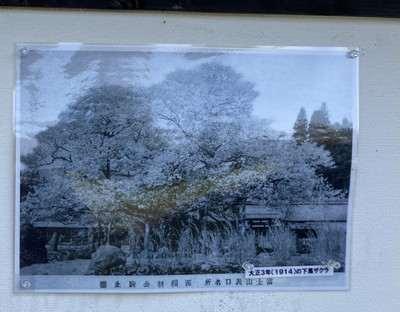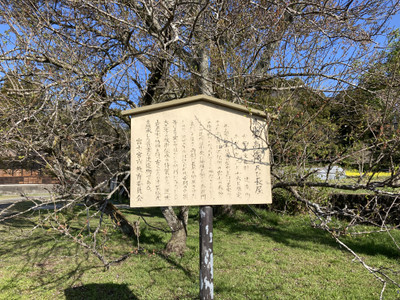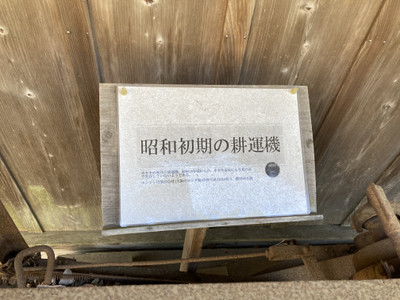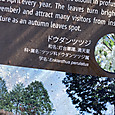今日の退任式で、子どもたちに宿題を出そうと思います
今日は令和7年4月15日。
今日は前勤務校での退任式があります。
退任式で、2〜6年生の前でお話をしなくてはなりません。
どんなお話をしようか。
再雇用の身なので、順番ではラストになるでしょう。
聞く側の子どもたちにとっては、
「これで最後だ」とホッとしたところでの登場。
2年間の在校中に、担当した子どもは30人。
卒業した子どもが4人いるので、
在校生の中に26人いることになります。
2年〜6年の全ての学年にいます。
在校生の中に、担当した子どもがいるのはありがたい。
小6や中3を担任した後だと、担当した子どもがいない状況。
何を話すのか難しくなります。
実が昨日の晩に、いいことを思いついています。
今まで退任式で話してきたこととは、全く違う内容。
先日、山に行った時の出来事がきっかけです。
参考:ここでも道草 シャクトリムシが糸を登っていくシーンを目撃(2025年4月13日投稿)
在校生に宿題を出すという内容です。
ちょっと準備が必要ですが、こんな内容です。
糸にぶら下がったシャクトリムシの模型を作っておいて
子どもたちに見せます。
「こんなの見たことがある人?」と聞きます。
何人かいるでしょう。でもあまり多くないと思います。
「これは、葉っぱや枝にいたシャクトリムシが、
他の生き物に襲われそうになった時に、
葉っぱや枝から落ちて、逃げた様子です。
とっさに糸を口から出して、ぶら下がります。
地面まで落ちちゃうと、蟻にやられてしまうので、
地面まで落ちないように、ぶら下がっているんです」
「この後、どうすると思いますか」
「シャクトリムシは、また上まで戻るんです」
「どうやって戻ると思いますか」
「先生も今まで、上に戻っていくシャクトリムシを
見たことがありませんでした」
「聞くところによると、上に戻っていくやり方は、
シャクトリムシの種類によっていろいろあるようです」
「この前の土曜日に、山登りに行って、
先生は、初めて、上に登っていくシャクトリムシを見ることができました」
「びっくりする登り方でした」
ここで模型によってその登り方を教えます。
「皆さんに宿題です」
「暖かくなって、虫が動き出しています」
「もしかしたら、糸にぶら下がったシャクトリムシを見るかもしれません」
「もし見る機会があったら、その登り方を観察してください」
「虫によって登り方は違うそうなので、見つけたシャクトリムシが
どうやって登るか観察するのが宿題です」
「その宿題が達成できたら、担任の先生に連絡して、
様子を伝えてください」
「そして、担任の先生、申し訳ありませんが、
スズキ公務のメッセージ機能を使って、平尾小学校の私まで、
その子の報告をお伝えください。」
「もしかしたら、ご褒美を届けるかもしれません」
こんな宿題を出しておいて、次のように言います。
「この2年間、◯◯◯小学校では、こんなように面白い勉強を
やらせてもらってきました」「いい2年間でした」
「一緒に勉強ができた2年間は、大切な思い出となっています。
ありがとうございました」
「新しい学校でも、面白い授業をたくさんやりたいと思って、
現在準備中です。」
「皆さんも面白いことをたくさんしてくださいね」
「そのためにも、先生からの宿題に挑戦してください」
「以上で、あいさつを終わります。
ありがとうございました」
こんな展開はどうでしょう。
この2年間を彷彿させるような内容であるし、
現在の自分らしさを出すことができます。
他の先生と被る話ではきっとないと思うので、
新鮮な気持ちで、子どもたちは話が聞けるだろうし、
次の学校がどこなのかも、話の中で言うことができます。
模型という具体物があり、つかみはOKです。
言う内容の方向性は決まっているので、
話すことを暗記したり、メモを読むことなく、
授業の時のように、リラックスして話ができる可能性高し。
我ながら、いいことが思い浮かんだと思います。
問題は、今から模型が間に合うかどうかです。
現在、朝の5時45分。
退任式は午後2時から。
さあ、思いついたことを実現できるかどうか。