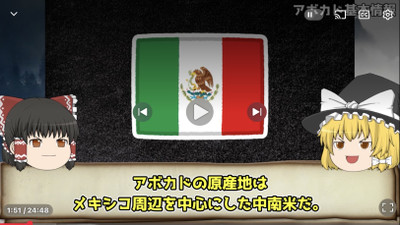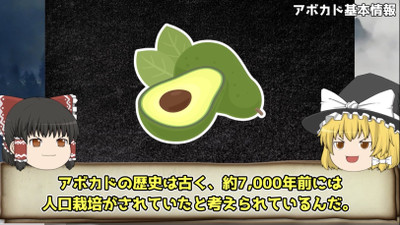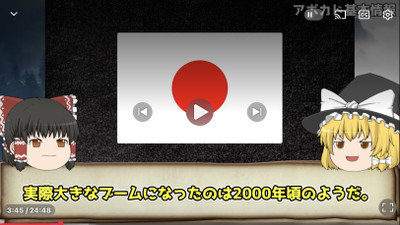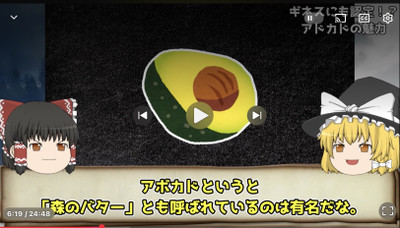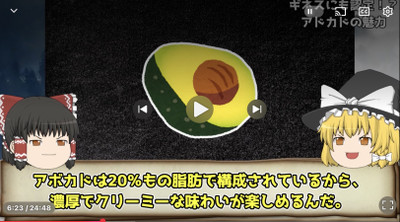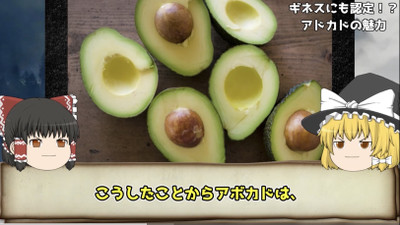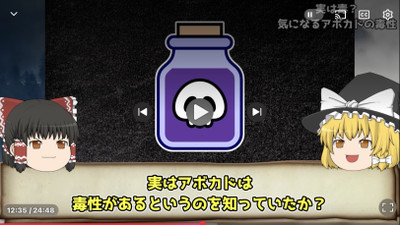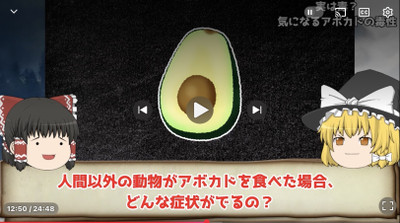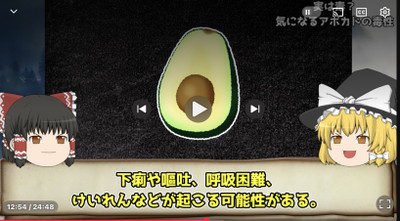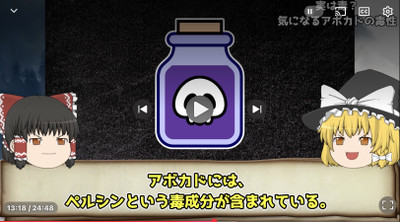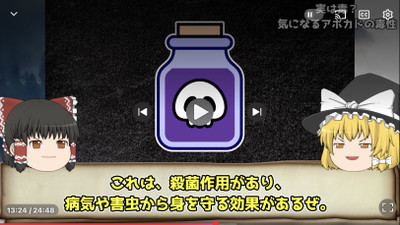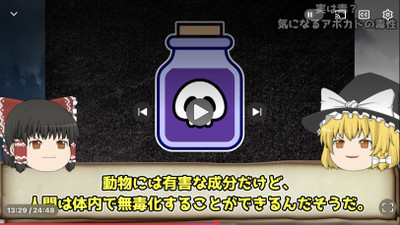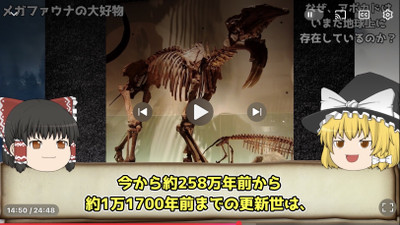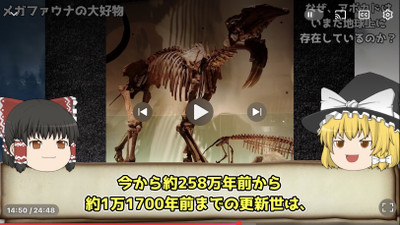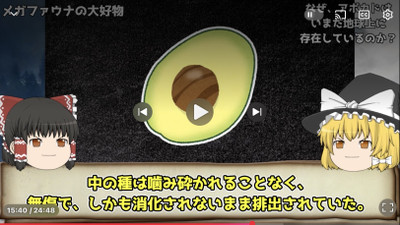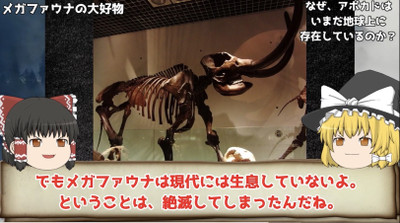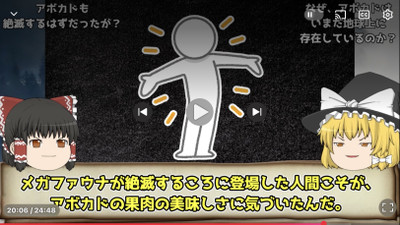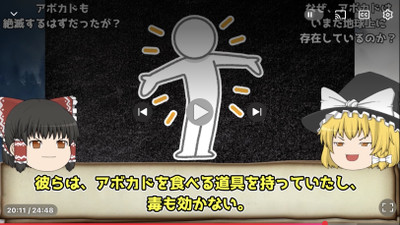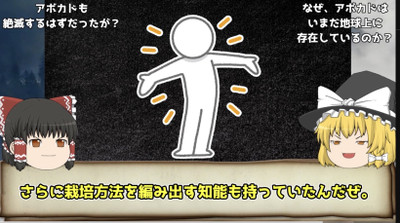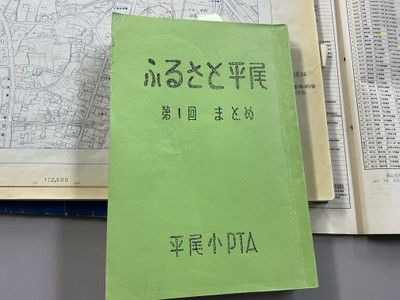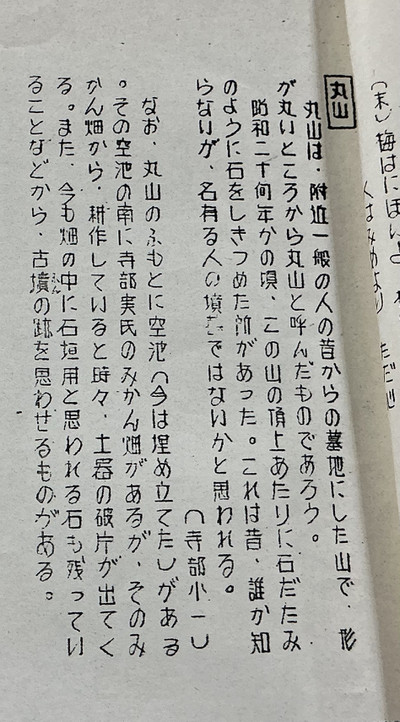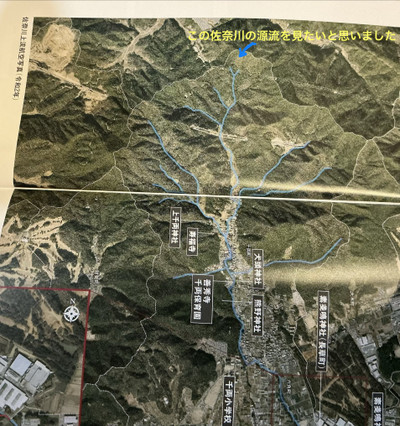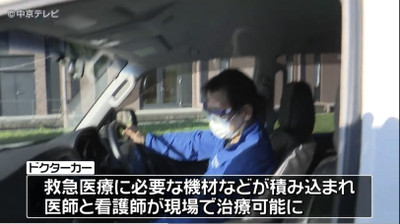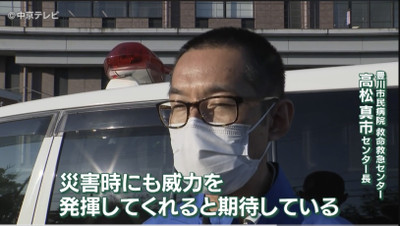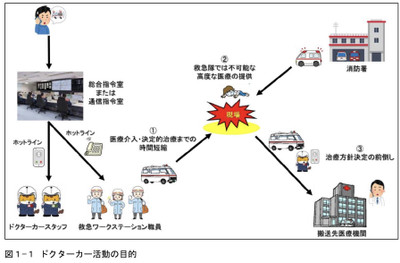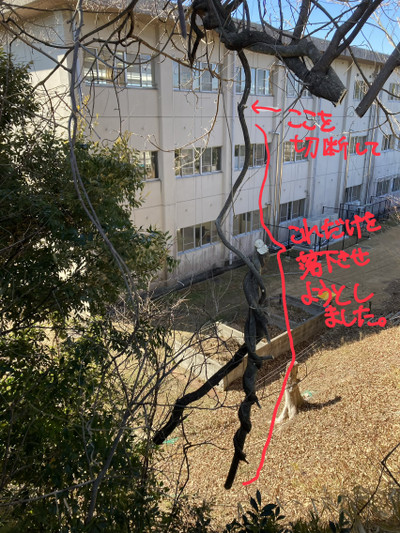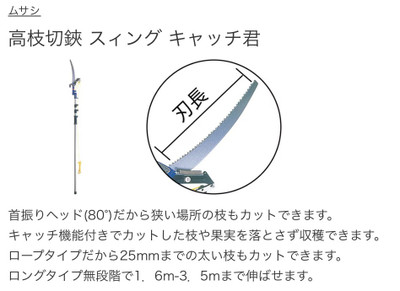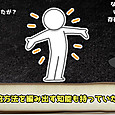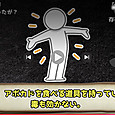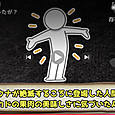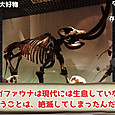動画「アボガドとは何者なのか?」を読み物にしてみました
今日は令和8年2月16日。
今朝は、朝7時から開いているスーパーに行って、
授業の浮き沈みの実験で使うアボガド等を買って、
出勤しました。
そして授業で実験をしました。
今朝買ったアボガドは、水に入れると沈んだり浮いたりして、
最後はゆっくり水槽の底面に沈みました。
このアボガドは、まだ熟していなくて、
油分が行き渡っていないといいうことでしょうか。
アボガドに関する動画を昨晩、今朝と何本か見てきました。
この動画の内容を、ここに記録しておきたいです。
YouTube: 【ゆっくり解説】13000年前に絶滅するはずだった…?「アボカド」とは何者なのか?を解説/繁殖の謎と人間社会の弊害
今回のスクリーンショットは、▶️つきで作りました。
効率的だったので。
邪魔だという人は、動画を見てください。
Pear=梨
アボガドの表面を触らせて、どの動物なのか予想させるのは面白い。
今日は2人に聞いたけど、ワニが出ませんでした。
なるほど。
この点は私は知識として得ておいて、子どもには言わないでおこうかな。
男の子には言っていいかな。
これは意外でした。
それだけ栄養を取り込むから、栄養価の高い果物になるんですね。
そうだよね。子どもの頃、若い頃には食べた覚えがないです。
最近、よくアボガドを持つので、「ヘタが浮き、皮との間に隙間」は
実感としてよくわかります。
「森のバター」と言われているのは、
今回のアボガドの勉強をしていて初めて知りました。
今回私は省略しましたが、アボガドの含む栄養素が
動画では数多く紹介されていました。
その挙げ句の「こうしたことからアボガドは」です。
「ペルシン」初耳です。
「人間は体内で無毒化」
人間てすごい。
ダイオキシンも人間には毒性がないと言われます。
また後日、記事にします。
今、こんなことができる動物はいない。
そもそも他の動物には有害なアボガド。
メガファウナたちは大丈夫だったようです。
巨大ですからね。毒も回らなかったかも?(勝手な予想です)
動物を介さずに、落下しただけだと、親木の下で目が出ます。
栄養面でも、日光量の面でも、育つのが難しかったようです。
あとで出てくるかな?メガファウナの糞がいい栄養になったようです。
メガファウナが絶滅した原因は、気候変動説と人間による説が
あるそうです。
メガファウナの絶滅で、アボガドの命運は尽きたという事態に。
「命運が尽きた」よりも「存亡の危機」と言った方が良かったですね。
アボガド。
調べたら、すごい果物だとわかりました。
アボガドと人間は縁があった食べ物でした。
日本人は2000年頃からの付き合い。
食べられて良かった。
以上の歴史を踏まえて、これからはアボガドを食べよう。