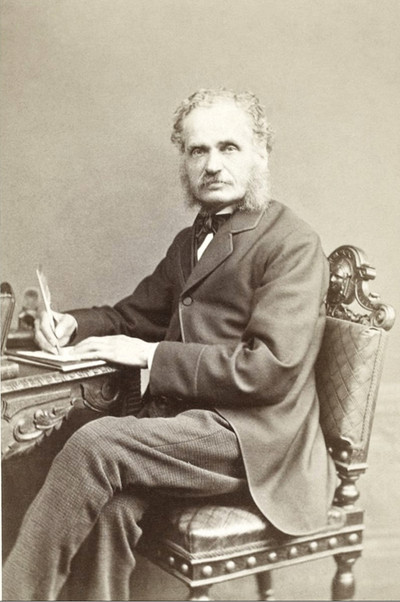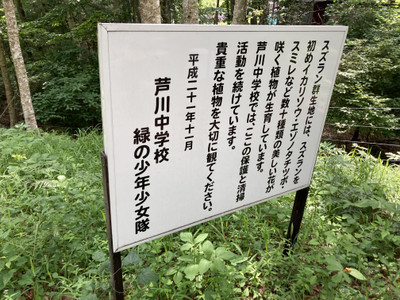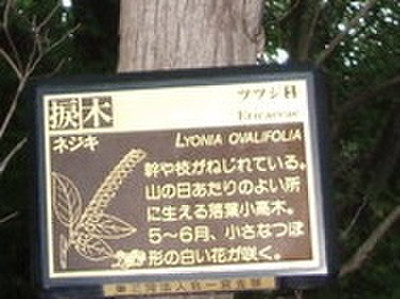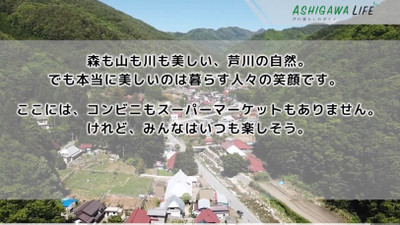今日は令和7年7月22日。
7月12日のこと。
この日は、地元の小学校体育館でレクリエーション吹矢をやりました。
月に2回、第2と第4土曜日の午後、都合のつく時には参加しています。
レクリエーション吹き矢に参加したことで、
手に入れた2種類の写真を紹介します。
地元の小学校の駐車場に車をとめて、
体育館に向かう時に目に入ったのが、
スイカ。


小さなスイカが、赤い網に入って宙ぶらりん。
こうやってスイカを育てることもできるんだと、
これは珍しいと撮影しました。
調べると、スイカの空中栽培というようです。
このサイトを参考にしました。
あまいスイカ スイカの空中栽培はスペース不要!ネットや支柱で吊るして収穫♫
このサイトにあった空中栽培のメリット・デメリット。
【メリット】
- 限られたスペースの中でもスイカを栽培することが出来る
- 目線の位置が上がるので、目視での管理がしやすくなる
- プランターからの空中栽培であれば、連作障害のリスクが下がる
- 通気性などを確保したまま栽培することが出来る
【デメリット】
- 大玉スイカを栽培する場合はしっかりとした支柱やある程度の土地が必要
- 支柱やネットなど、追加で道具を準備する必要がある
- ベランダなどでは鳥対策などが必須
-
なるほど。限られたスペースで作る必要が、
学校での栽培では必要なことが多いです。
目視での管理がしやすいというのもいい。
私も5年ほど前にスイカ栽培をした時に、葉っぱに埋もれたスイカを
見つけるのが大変でした。
今度、7月26日にリクリエーション吹矢に行く予定なので、
スイカがどうなったか楽しみです。
もう1枚の写真。

私が撮った写真ではなく、レクリエーション吹矢のお世話役の方が
撮った写真。
私が虫好きであると思われていて、きっと喜ぶと思って見せてくれました。
いいですね。その方も私も初めて見る蛾です。
色がいい。
その方は、すでに名前を調べてきてくれてあって、
「ちょっと覚えにくいんだよ」と言って教えてくれました。
「ピュラウスタ」
これは覚えにくいです
後日調べてみました。
少し前進しました。
「ピュラウスタ」は英語名「Pyrausta inorna」
調べたところ「日本名なし」というサイトもありましたが、
日本名があるサイトもありました。
ピンク色の小さな蛾。紫のサルビアにつく外来種。
「アメリカピンクノメイガ」
日本人には、こちらの名前がいいです。
アメリカ生まれの蛾。
日本では2019年に発見された蛾。
何かアメリカから届いたものに、卵や幼虫が入っていたのかな。
とても似た蛾がいます。
「マエベニノメイガ」です。
これと比較することで、2つの蛾を認識できますが。
東京昆虫館
このサイトに両種の写真あり。
一目瞭然です。

「マエベニノメイガ」

羽全部がピンク色(ワイン色)なら「アメリカピンクノメイガ」
羽の中央にオウド色があるのが「マエベニノメイガ」
アメリカピンクノメイガの幼虫の食草は、
ブルーサルビア。
世話役の方のお庭には、ブルーセルビアがあるのかな。
以上です。
記事にしたいことは、毎日何か行動すると目に入ってきます。
こんなふうに。