「冬来たりなば、春遠からじ」/ヒメオドリコソウ発見
今日は令和7年2月2日。
今日は節分。明日は立春。
アレチヌスビトハギを撲滅するために、
ほぼ毎週通っている公園。
昨日、行ってきました。
アレチヌスビトハギは1本も発芽していませんでした。
まだオフシーズンのようです。
プロ野球のキャンプがスタートしました。
CBCの「ゴゴスマ」で、天気予報士澤朋宏さんが、
今の時期のことを微妙な表現をしていました。
「1年で一番寒いのは、1月28日、29日、30日あたり。
2月1日、2日あたりは、寒いけど、暖かい方に向かう兆候が
見られる」
そんな内容だったと思います。
たった数日の違いですが、本当か?と思うところと、
そうかもしれないなあと思うところがあります。
「1月の終わり」と「2月のはじめ」
月が違うのも大きな理由だと思います。
1月は容赦なく寒い月、2月は梅も咲き始め、春が混じる感じ。
もちろん年によって違うかもしれませんが、
もうじき64年生きてきた体験の積み重ねもあって、
沢さんの説は、否定できないものがあります。
なんせ、1年の太陽の動きは、とても正確ですからね。
「冬来たりなば、春遠からじ」
いい言葉です。
イギリスの詩人パーシー・シェリーの詩の日本語訳。
原文は、
"If winter comes, can spring be far behind? "
直訳すると、
「冬が来るなら、春はその遥かあとであろうか?」
う〜ん?です。
もう少し調べてみます。
原文では?がついているけど、日本語訳には?が無いことに
触れています。
なぜか。上のサイトから一部引用。
「冬来りなば」は、現在形で「冬が来るなら」と訳すのが正解という
ことになります。それを踏まえた上でさらに疑問文に訳すと、「冬が
来るなら、春がはるかに遠いことがありえようか?」となります。こ
れを反語的に訳すと、「春遠からじ」(春は遠くないぞ・春は近いぞ)
となります。
わかったような、わからんような。
でも、訳者は、直訳せずに、
詩人が言わんとしたことを理解して、
この名訳を誕生させたのでしょう。
どなたの訳なのか、発見できませんでした。
人生、辛い時があっても、必ずいい時が来るという
前向きな心になれる言葉でもありますが、
自然現象的にも、あり得ることです。
水曜日から特に寒くなるとのこと。
「冬来たりなば、春遠からじ」が似合うタイミングです。
ほぼ毎週通っている公園で、昨日発見した
ヒメオドリコソウの花。
春の野草です。
もう咲いていました。
やっぱり「春遠からじ」だと感じました。


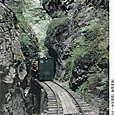
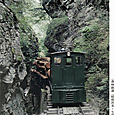
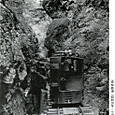
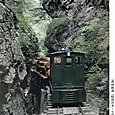
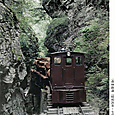







コメント