「見て分かる困り感に寄り添う支援の実際」から引用
今日は4月2日。
最近読破した「見て分かる困り感に寄り添う支援の実際」(佐藤曉著/学研)から
せっせと引用します。下記のところで引用した本の続編です。
※ここでも道草 「発達障害のある子の困り感に寄り添う支援」からの引用
たとえいつもの時間であっても、ぶっつけ本番では
その場の状況が読み取れないのが発達障害のある子どもである。
その時間に何が行われることになっていて、
自分は何をしたらいいのかを、
この子たちには前もって伝えておきたい。
これがスケジュールづくりの基本である。(12p)
楽しい活動がこの先にあるということを伝えるのが
スケジュールなのだ。(13p)
活動ごとに空間が区切られた幼稚園だ。
活動と場所とが一対一で対応していると、
発達障害のある子どもにはとても分かりやすい。
「場所の構造化」といわれるルーツがこんなところにある。(14p)
すぐにできる配慮は、注意をそらしたり、
衝動性を誘ったりする要因を減らすことである。
教室の本の棚の中が気になってしかたがない子どもには、
布で目隠しをする。
教室外の環境がひどく子どもの気を散らしているようなら、
ガラスにフィルムをはる。
当然、教師の机の周辺も整理しておきたい。(15p)
集団づくりは、クラスの「人環境」を整備する上でもっとも大切なものだ。
教室内でのことば遣いや立ち振る舞いは、
常日ごろからどの子にも教えていきたい。
一度崩れた言語環境や行動規範は、そう簡単に修復できるものではない。(18p)
「この先生についていけば大丈夫」、
どの子もそう思えるような学級づくりを目指したい。
教師のリーダーシップがあってこそ、
安心して生活できる学級集団ができあがるのだ。
「人環境」はこうしてつくられる。(18p)
教師の自己チェック(中略)
何らかの指導の手だてを講じているか
〇子どもが何を求めているのか、
また何に「困り感」を抱いているのかをくみ取っているか。
〇「子どもにつけたい力」は何か、明確になっているか。
また、それを身につけさせるための具体的な手だてがあるか。
〇子どもが好きなことや得意なことを、
授業や学級経営に取り入れているか。(20p)
発達障害のある子どもには、学習規律の乱れた教室ほど居心地の悪い所はない。
授業中に周りの子どもたちがバラバラなことをしていたら、
子どもは誰をモデルにしたらいいのか分からなくなる。
また、かってなおしゃべりが横行している教室は、
発達障害のある子にとって、ひどく脅威である。
人を傷つける発言がまかりとおり、いつ何を言われるか分からないと、
心配でおちおち授業も受けられないのだ。(27p)
規律を定着させるためには、クラス全体で取り組まないと意味がない。
というよりも、時間規律を教えることは、集団づくりの第一歩なのである。
たとえば「ベル着」は、一週間も繰り返せば、
すぐに目に見える結果として出すことができる。
みんなで挑戦してできた喜びを体験させる。
これが教師の仕事である。(28p)
課題を早くすませてしまい、立ち歩いたり、
周りにちょっかいを出したりする子には、
空いた時間にすることを考えてあげたい。
迷路やことばのかくれんぼなど、
子どもが好みそうなプリント類を用意しておくといい。(31p)
何が分かっていないのかというと、
「毎日決められた時間内に準備することを教師が期待しているということ」なのだ。
周りの子たちは、それがほぼ直観的に分かるのだが、
発達障害のある子どもにはなかなか伝わらない。
休み時間にすべきことも同じである。
教師の期待が届きにくい子どもたちには、
あたりまえと思うことも、書いて伝えることが大切だ。(32p)
全部できたら、好きなシールをはる。
終わったあとに、子どもが望むことをほんの少しでも用意するのがコツである。
ただし、こうした手だてには賞味期限があるので、
「今日は乗りがもうひとつだったな」と思ったら、
次の日には目先をちょっと変えてみる。
そういう教師の勘は、磨かないといけない。
むしろ、「手だては使い捨て」くらいの気持ちで、
日ごろからいろいろな手だてを考える習慣をつけておきたい。(39p)
教育支援の向かう先
「困り感」軽減→「安心感」の保障→「イケテル感」の育成
学校でのようすが気がかりな保護者は、
ノートがきれいに書いてあれば、それだけでも安心する。
頑張ったことが形に残るのが、ノートである。
ていねいに指導したい。(49p)
作文の技法に限らず、教わったことは、
使う機会がなければけっして定着しない。
技法というのは、子どもができるようになるまで何度も何度も教えていくものである。
手間暇をかけずに、「なかなか定着しない」とぼやいていてもしかたないのだ。(50p)
教師の指示を受けて行動している周りの子どもたちから「学び方を学ぶ」ことが、
発達障害のある子にはとても大切である。(63p)
12時になったら、みんなが楽しみにしている「ウーフの本」を読んでもらうことになっている。
ささやかな「向かう先」だ。(中略)
子どもたちが安心して生活できる「いつもの形式」が、この学級にはある。(68p)
プリント学習にも、ちょっとした「向かう先」を用意しておくと、
子どもたちの動きはかわる。(69p)
同じ活動を繰り返すことによって見通しがもてるようになった子どもたちは、
次々に推移していく活動の流れに、
安心して身を任せられるようになる。
そうなってはじめて、子どもは持ちまえの力を発揮し始める。
「形式」が大切だという言い方をすると、
子どもを型にはめてしまうように聞こえるかもしれないが、
それはまったく違う。
いつも決まった形というのは、子どもに安心感を与えるのだ。(70p)
いつもの形式は、子どもたちは裏切らない。
「向かう先」があると、子どもたちの体は前を向く。
「向かう先」を得た子どもたちの表情は活気に満ちていた。
子どもたちがほんとうに望んでいることは、
自由にさせてもらうことよりも、形式のある活動のなかで、
保育士との絆を深めることなのかもしれない。(71p)
発達障害のある子どもたちの場合、目に見える「向かう先」がないと、
学年が上がるにつれて生活が崩れがちである。(中略)
とにかくその日の指導に追われがちな個別学級である。
子どもの活動に「向かう先」があるかどうか確かめてみてほしい。(74p)
発達障害のある子どもは、周りの子たちの心ない一言にひどく傷ついている。
それだけではない。
教室の言語環境が悪化していると、使ってほしくないことばばかりを、
選択的に覚えてしまうのがこの子たちなのだ。
ことばの乱れは、将来、その子にとんでもない不利益をもたらす。(95p)
小学校二年生を受け持つ平松先生が実践してきたことは、
担任の思いに答えてくれた子どもの行動や言動に
「意味づけ」をすることだった。
授業や帰りの会など、事あるごとに
「あなたたちのしてくれたことが、先生がみんなに期待していたことなんだよ」と、
感激の気持ちをこめて語り続けた。(103p)
オーダーメイドマニュアルの作成手順
作り方はいたって簡単である。
手順1
日ごろその子とかかわりをもっている保育士や教師が、
うまくかかわれたときの手だてを、一枚の紙に一つ書きとめる。
「こんな場面で、こんな手だてをうったら、子どもがこうした」というエピソードを書き、
できればかかわりのポイントを短いことばでまとめておくと、
他の人が読むときに便利である。
手順2
書かれた実践を集めて、整理する。
このとき専門家に意見を求めてもいい。
手順3
それを小型のクリアブックにはさむ。
手順4
必要に応じて差し替える。
これだけである。うまくいった支援実績を寄せ集め、
「こうしたらこの子はうまく動ける、喜んでくれる」という資料をつくるのである。(119p)
子どもに安心感を保障するには、
「見通しと向かう先」「できた・分かった体験」「人間関係」という
三つの要件が必要だ。
それぞれに沿って、支援経過を振り返ってみよう。(124p)
小学校も三年生になると、我が子の態度に保護者が負けそうになることがある。
そんな保護者を精神的に支えるとともに、
行き詰ったときの脱出法をいっしょに考えてあげたい。(157p)
発達障害のある子どもには、小・中学校うちに、
さまざまな経験をさせてあげたい。
この子たちは、やったことがないことに極端な不安感を抱いている。
反対に、一度やってみて楽しかったり、いい結果が出たりすると、
それがとても大きな自信になるようだ。
高校生以上になったとき、発達障害のある子どもが
自分からやりたいと申し出ることは、たいていの場合、
家族がしていることか、かつて小・中学校のときに、
なんらかの形で自分が体験したことなのである。(159p)
動機づけになりそうなものを見つける
家庭での支援を成功させるためには、子どもの嗜好を把握しておきたい。
子どもが楽しみにできることを「向かう先」にして、
生活を組み立てていきたいからだ。
子どもの好みをチェックする観点として、次のようなものが考えられる。
〇食べ物 〇持ち物 〇キャラクター 〇遊びや余暇 〇外出先(中略)
一方、子どもが苦手なものもおさえておこう。
脅してはいけないが、どうしてもというときには使える。(167p)
保護者と話をすると、そのたいへんさが身にしみるとともに、
子を思う気持ちや、保護者の頑張りに頭が下がることがある。
教師が保護者から学ぶことが多いと感じているときは、
たいてい保護者のほうも学んでいる。
どんな小さなことでもいい。
相手のすてきなところを感じ取るアンテナを教師は持ちたい。(168p)
周囲の保護者には、二つの側面から啓発活動を進めたい。
一つは、発達障害に関する一般的な知識の提供である。(中略)
もう一つは、学校の取り組みについてである。
この学校では、支援が必要ならどの子どもにも手厚いケアをするのだということを、
印刷物などをとおして啓発しておきたい。(181p)
たくさん引用しました。引用することで、自分の血や肉になってほしいです。

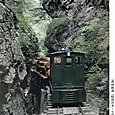
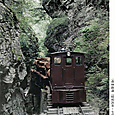










コメント