黙祷の歴史
今日は令和4年8月29日。
前記事に引き続き、関東大震災のこと。
今日の朝日新聞朝刊に黙祷のことが載っていました。
関東大震災が関係していました。
記事を引用します。
汽笛を合図に、路上の人々は1分間、無言で祈った。
10万を超える犠牲者が出た関東大震災から1年、1924年9月
1日の東京・銀座の通りの様子を、新聞は伝えている。多くの店が
休業する中、汽笛が鳴ったのは、地震が起きた午前11時58分。
通行人だけでなく、路面電車も自動車も止まった。
東京市はこの日、追悼式を催し、1分間の「黙祷」を市民に提案し
た。これが日本の黙祷の始まりだ、と粟津賢太・上智大学客員研究
員(宗教社会学)は言う。翌年以降は黙祷の名で、ラジオなどで呼
びかけられ、全国に広がっていった。
粟津さんによると、黙祷は同時代の英国の「2分間の沈黙」がルー
ツ。1914年からの第1次世界大戦で英国は、約90万人の戦死
者を出した。停戦から1年となる1919年11月11日を追悼記
念日とし、国王は国民に2分間、日常生活を止め、戦死者を追想し
ようと呼びかけた。
「黙祷」の歴史を知りました。
黙祷は、特定の宗教によらないために、
受け入れられやすいやり方だと記事に書いてありました。
そう思います。
2019年11月11日。
100年後のヨーロッパで、黙祷が行われていたことを思い出します。

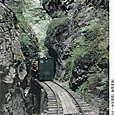
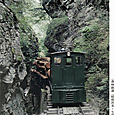
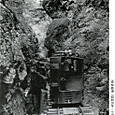
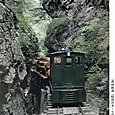
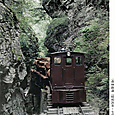







コメント