「函館の大火」①/「蟹」と「工船」
今日は令和元年11月11日。
この記事に書いたこと。☟
※ここでも道草 「雪虫の飛ぶ日」⑥/函館大火(2019年10月29日投稿)
この本が読んでみたくなりました。
「函館の大火 昭和九年の都市災害」
(宮崎揚弘著/法政大学出版局)
2017年刊行で、新しい本であることが魅力。
図書館に置いていないのが残念。
買って読むか迷っています。
でもきっと好奇心に負けます。
やっぱり好奇心に負けて、購入しました。
中古で購入。3600円の本が2493円(送料含)で
手に入りました。
そして読みました。
勉強になりました。
昭和9年(1934年)3月21日の函館の
大火に関する詳細な本です。
さっそく引用していきます。
函館山の山頂からは眼下に市街地が広がり、南は下北半島、
津軽半島を望み、道内有数の景勝地をなしている。
夜景は日本三大夜景(函館、神戸、長崎)、
世界三大夜景(函館、香港、ナポリ)のひとつとして有名である。
しまし、夜景は函館山が市民に開放された現在についてのみ
言えることである。昭和9年の大火当時、函館山には
明治32(1899)年以来設置された
函館要塞(後に津軽要塞と改称)があり、
民間人は立入り禁止であった。
そのため、美しい景観は知られていなかった。
(5p)
函館山が、市民に開放されたのは昭和21年(1946年)の
12月のことでした。参考:Wikipedia
(函館港の)特色は青函航路の拠点港であったことにある。
元々それは日本郵船が始めたが、実情に即していなかったので、
明治41年鉄道院が新造船を投入して青函連絡船の運航を
開始した。
(18p)
青函連絡船は、上記の通り明治41年(1908年)から、
昭和63年(1988年)まで運航していました。
参考:Wikipedia
そうかあ、平成時代には運航してなかったのですね。
私は1985年に乗船しました。あれは昭和だったんだ。
まあそうか。
函館は大正·昭和期には変ることなく出稼者の中継基地であった。
季節的には春、秋に賑わう。出稼者は出身が道内、東北、
北陸の諸地方に集中している。(中略)
沿岸漁業が衰退したため、出稼漁夫·雑夫は
北洋漁業へ活路を求めて転進した。
そうした北洋漁業へ出漁する船の出航地は多くが、
関係者の集散しやすい交通の要衝、函館であった。
(29p)
工船は船中に缶詰工場を備える大型船だが・・(略)
(36p)
出稼ぎの人たちは、沿岸漁業で鰊(にしん)や鰯(いわし)を
獲っていましたが、不漁になると、遠くオホーツクの海や
ロシア近くの海にまで出かけて行きました。
獲れるものは鱈(たら)、鱒(ます)、鮭(さけ)、
そして蟹(かに)等でした。
「蟹」と「工船」で思い出すのが、小林多喜二の小説「蟹工船」
小説が発表されたのは昭和4年。
函館の大火の年に近いです。
知っていますが、まだ読んだことがない小説。
近々読もうかな?
「函館の大火 昭和九年の都市災害」は、大火当時の函館が
どのような都市であったかを細かく紹介しています。
今回は、そこからの引用です。

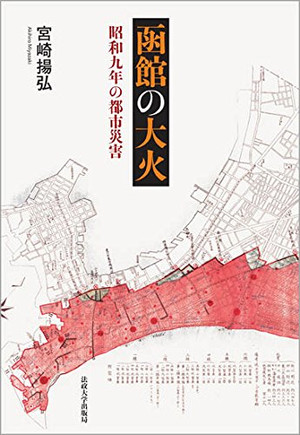












コメント