大きく育ったビカクシダに出合う
今日は令和7年4月30日。
この植物の名前は「ビカクシダ」
シダの仲間です。
こんな巨体のシダは見たことがないと思います。
今日(4月30日)に撮影しました。
私の住む町内会地区のある家で撮影させてもらいました。
私は町内会で電子回覧板「結ネット」を担当しています。
「町内会花図鑑」シリーズというのを連載中で、
いろいろなお宅に行って、撮影させてもらって、
結ネットで紹介しています。
今日は、桃色のフジの咲くお宅を訪ねて撮影させてもらっていたら、
他にもこんなのがあるよと教えてもらったのが
ビカクシダ。
「カク」は「角」
葉っぱが鹿の角に似ていることから、
この名がついたそうです。
では「ビ」は?
持ち主の方も、「ビ」については思い出せませんでした。
「美」ではないようです。
調べてみます。
ここに答えがありました。
引用します。
ビカクシダは熱帯に生息し、樹木や岩盤に貼りつきながら生長する着生
植物です。不思議な響きの名前ですが、「ビカク」は漢字では「麋角」
と書き、「ヘラジカの角」を意味します。
特徴的な葉の形がシカの角に似ていることから、「麋角羊歯」と呼ばれ
るようになりました。また、垂れ下がった葉がコウモリの羽のように見
えることから、別名「コウモリラン」とも呼ばれます。
「麋」は「オオジカ」とも読みます。
参考:漢字辞典
そしてヘラジカはオオジカとも呼ばれます。
さらに「となりのカインズさま」には興味深いことが
書いてありました。引用します。
ビカクシダの種類について書いたところです。
ビカクシダ ビフルカツム(今回、お宅にあったもの)
ビフルカツムはビカクシダの中でもっとも一般的な種類で、園芸店
だけでなくインテリアショップなどでも手に入りやすくなっていま
す。
見た目はその名の通りヘラジカの角に似た大きな胞子葉と、根元を
お皿のように覆い隠す貯水葉が特徴です。
丈夫で温度や明るさの変化にも強いため、初心者の方におすすめの
品種です。
そうなんだ、あの角の葉は胞子葉だったのですね。
どうやって胞子が作られ、どのように増えるのか興味あり。
また調べましょう、後日。
持ち主さんの話によると、ビカクシダは小さな植木鉢での栽培で
始まったそうです。
その植木鉢は、巨体のビカクシダの下に隠れていました。
温室でないと育たないと言われたのに、こんなに大きくなったと
持ち主さん。
近所にこんな面白い植物があったなんて。





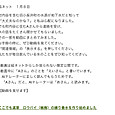

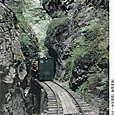
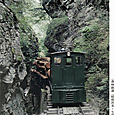
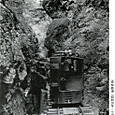
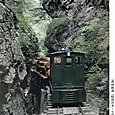
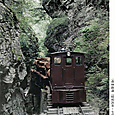



コメント