20240601大川入山登山⑥ ハネカクシ ハルゼミ
今日は令和7年3月30日。
前記事の続きで、昨年6月1日に登った
大川入山の報告です。今度こそ最終回です。
この虫にビックリです。
この虫、ハネカクシなる虫でした。
初めて知った虫です。
習性が面白いです。
このサイトから引用します。
大部分の種で上翅(鞘翅)が非常に小さく、後翅はその下に小さく
巧みに折りたたまれているため、腹部の大部分が露出しており、
一見すると短翅型のハサミムシやアリのような翅のない昆虫に見え
る。しかし実際にはほとんどの種類が機能的な後翅をもっていて、
必要に応じてそれを伸ばしよく飛翔する。着地後は再び後翅をたた
み隠し、もとの翅の無いかのような姿に戻る。これが「翅隠し」と
よばれる所以である。前述のように非常に種類が多いことで有名で、
1科に含まれる種数の多さでは動物界全体から見てゾウムシ科に次
ぐと言われている。世界には数千属に属する5万8000種以上が知ら
れているが、実際には10万種以上あるとも言われ、日本国内だけで
も数百種の未記載種がいる可能性が高い。歴史も古く、約2億年前
の中生代三畳紀の化石が知られている。
「翅が無いかのような姿」
私が見たのは、その姿だったようです。
ビックリです。
そんな虫がいるんだ。
こんな文章もありました。
日本では1990年代後半になってから、これを専門に扱う研究会であ
るハネカクシ談話会を中心に研究が活発化してきており、若手の専
門研究者も少しずつ増え、多くの新発見がなされつつある。
「ハネカクシ談話会」が楽しそう。
このサイトから一部引用します。
ハネカクシ談話会はハネカクシ上科 Staphylinoidea という甲虫(
昆虫綱,コウチュウ目)の生物学的研究を行う団体です。ここでいう
生物学的研究とは、分類学的、系統進化学的、生態学的、生理学的、
生物地理学的、地域ファウナ学的等、あらゆる生物学的側面からの研
究を指します。
ハネカクシ談話会は1996年6月から活動を開始し、1997年1月1日
に正式に発足しました。事務局は当初千葉県立中央博物館に置いてお
りましたが、現在、国立科学博物館動物研究部に移しております。
(中略)1999年2月現在で会員数が64名となっております。
ハネカクシ談話会の活動は本部がある関東地区を中心に企画され、年
1回の研究発表会(6月頃)と同じく年1回の採集会(11月頃)が
中心です。また、年3回連絡紙「ハネカクシ談話会ニュース」を発行
しております。
「ハネカクシ談話会ニュース」は、ネットで注文して
手に入れることができるようです。
こんな会ができるほど、ハネカクシは魅力的なのでしょう。
動画を探しました。
きっとあると確信して探しました。
ありました。
YouTube: ハネを隠すハネカクシ rove beetle wing folding
この動画の58秒から、
ハネをしまうところが見られます。
お尻を使ってしまうなんて、想像できず。
面白い。
動画の写真を並べます。
もうすぐ64歳になりますが、
一生出合わないことになっていたかもしれません。
幸運でしたね。
次の動画は、ハネカクシがハネを出して飛び立つところです。
48秒から注目です。
ハネは一瞬で出ます。
う〜ん、ハネをしまう方が面白かったなあ。
この知識を得たことで、登山がさらに楽しみになりました。
実際にハネをしまうところを見たいです。
いやいや、捕まえたいですね。
以上でハネカクシの記述は終了。
まもなく登山もゴールです。
横岳頂上付近でセミの抜け殻を発見。
6月1日なので、ハルゼミと思われます。
草でわかりにくけど、ここが今回の登山道で、
最も危険な場所。
踏み外せば、かなり落下します。
皆さん、ご注意を。
下山時には、長く感じる根っこ道。
この根っこ道が終わると、登山はまもなく終了です。
この写真を撮ったのが15時30分。
山に8時間余りいました。
大川入山はやっぱり登り甲斐のある山です。
やり遂げたという達成感が得られます。
今年も登りたい山です。
以上で報告終了。
















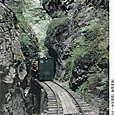
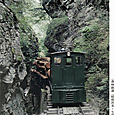
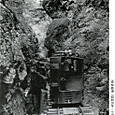
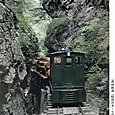
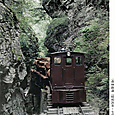







コメント