本「高熱隧道」④ 多くの犠牲者が出ても工事が継続された理由
今日は令和6年3月20日。
前記事に引き続き、
「高熱隧道」(吉村昭著/新潮文庫)を読んで、
印象に残った文章を引用していきます。
その頃、県警察部では、日本電力・佐川組の両者をまねいて、事故の
事後処理に対する見解をあきらかにした。 それは、工事の全面的な
中止命令に近いものだった。
「犠牲者をこれ以上出すのは、もうやめなさい」
部長は、ふりしぼるような声でくり返した。
藤平は、頭を垂れてその声をきいていた。 根津は仏が出ても遺族のこ
とは決して考えるな、と言ったが、遺体とともに宇奈月に降りてから
は、遺体にとりすがって泣き叫ぶ老人や女や子供たちの姿を毎日眼の
前で見てすごした。遺族たちの素朴な態度は、かれの胸を深く刺した。
かれらは泣き叫ぶだけで、肉親を死に追いやったはずの幹部技師や会
社に批判も憤りもぶつけてこようとはしない。 藤平たちが、神妙にか
れらに慰めの言葉をかけると、かれらは、ただ頭を深々と下げて、く
り返し礼を述べるだけなのだ。
死者をこれ以上出すのはやめろという警察部長の悲痛な言葉は、その
まま受け入れなければならない常識にちがいない。
これまで苦しんで工事をすすめてきた以上、全工事を完工させたいの
は山々である。が、黒部渓谷は、人間が挑むのは到底不可能な世界な
のかも知れない。
黒部の奥で工事をすることが無理だ、と宇奈月の町の者たちは言って
いるというが、かれらにとっては、欅平附近ですら秘境なのだ。まし
てその上流の黒部渓谷は、人間の足をふみ入れることのできない恐る
べき魔の谷であることを知っている。その渓谷で、工事をはじめ自分
たちは、かれらからみれば狂人としか思えなかったのだろう。
その結果は、多くの死者となってあらわれた。神秘的な黒部渓谷の自
然の力の前に屈する人間の敗北の姿として、かれらは恐れおののいて
それらの遺体をながめてきたにちがいない。
(157〜158p)
泡雪崩によって吹き飛ばされた志合谷宿舎の建物が、
大岩壁に激突しているのが発見され、犠牲者の遺体が
収容された後の場面です。
黒部渓谷が、当時どのように思われていたのかわかる文章です。
三月十八日、雪崩によるその春最大の鉄砲水が上流で発生し、阿曾
原谷は一時的な洪水状態に見舞われた。激流は宿舎の近くまで押し
寄せ、一階の炊事場には雪をまじえた水が流れこんだ。
水は間もなくひいて危険は去ったが、その日の午後、志合谷事故の
犠牲者全員に天皇陛下から金一封が御下賜されたことを、宇奈月事
務所から電話で知らせてきた。
藤平は、すぐ宇奈月までくだったが、迎えた根津もかれも、その一
名あたり二十五円の金額については、遺族たちの悲嘆をやわらげる
のに効果があるだろうという程度にしか考えなかった。そして、遺
族に対する自分たちの責任が、幾分か軽くなったような気持をいだ
いた。
しかし、その御下賜金の下附決定は、藤平たちの想像もおよばない
大きな波紋を周囲にひき起していた。殊に富山県庁と県警察部の反
応は大きかった。
かれらの黒部第三発電所建設計画第一・第二工区に対する工事の全
面的な中止の意志はきわめてかたく、それはほとんど確定的なもの
になっていた。たとえ中央本省から工事再開命令が出されたとして
も、かれらは犠牲の大きいことを理由に強硬な反抗をしめすにちが
いなかった。かれらは、黒部渓谷の特殊な性格を知りつくしていて、
そこで工事のおこなわれることがほとんど不可能であると判断して
いた。
しかし、御下賜金の下附決定は、かれらの態度をたちまち突きくず
してしまった。それは、かれらの批判をさしはさむ余地の全くない、
おかしがたい絶対的な力をもつ声として受けとられたのだ。
御下賜金の下附には、県側の強い意向をひるがえさせようとする中
央本省の政策的な工作もあったのだろうが、そうした事情に気づい
てはいても、県も県警察部も御下賜金の対象となるような重要な工
事を、自分たちの意志で中止させることは到底許されないことを知
っていた。それどころか、たとえ犠牲はどれほど多くとも、積極的
に工事続行に協力しなければならない立場にあることをさとったの
だ。
(169〜170p)
当時の天皇の権力、威力、権威を感じました。
これで、大きな犠牲を出したにもかかわらず、
工事は続けられました。
漸(ようや)く貫通の日が近づいたことに、藤平はあらたな感慨をお
ぼえていた。 加瀬組の放棄した阿曾原谷横坑と仙人谷本坑指定位置に、
それぞれ第一回の発破がとどろいてから七四二メートルの岩盤を掘鑿
(くっさく)してきたことになるが、死者は百七十名をかぞえ四・三
メートル強に対して人間一名が消えてしまったことになる。
人柱という言葉が、自然と胸に浮んでくる。難工事が予想される折に、
生きた人間を水底に沈め土中に埋めたのは神の心をやわらげるためだ
というが、自然はそのような形で犠牲を強いるのだろうか。 人柱は、
事前に神に供えられるが、百七十名の死者は、たとえそれが故意に犠
牲として供えられたものではなくとも、残忍な人柱と異なるところは
ない。
生きて作業をつづけている人夫たちの姿も、決して尋常なものとは思
われない。かれらの体は、熱さにおかされて脂肪分が失われ、骨と皮
のように痩せきってしまっている。そして、体中いたる所に、懲罰で
も受けたように火傷の痕が残されている。連れ立って坑内から出てく
るかれらに、藤平は、死の翳(かげ)りを色濃く見出して、思わず顔
をそむける。
しかし、順調に掘鑿がすすめば三ヶ月後には貫通するという想像は、
藤平の胸をときめかせた。たとえ人夫たちが亡者のように痩せこけて
しまっていようとも、かれらを督励して、切端にぽっかりと穴のあく
のを眼にしたいという願いが、切なく胸の中にあふれた。
(175p)
この文章を読んだ時には、私は働く日本人を思い浮かべていました。
しかし、その後に読んだ「黒三ダムと朝鮮人労働者」(堀江節子著/
桂書房)の内容に驚きます。働いていた人たちの多くは朝鮮人だっ
たということです。
藤平が感じている人夫に対する不安とか、人夫の犠牲があっても
工事を完結させたいという気持ちは、同朋の日本人ではなく、
別国の朝鮮人だからだったのではないのかと。
たくさんの犠牲者が出ても、人夫が反抗しなかったのも、
朝鮮人だからというのもあったのでは。
吉村昭さんは、朝鮮人が働いているのを知りながら、
朝鮮人を1回も出しませんでした。考えさせられます。







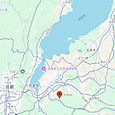





コメント