本「日本国紀 下」/「中国の旅」 国家総動員法の成立 ヒトラーへの妥協
今日は令和5年11月5日。
前記事に引き続き、
「日本国紀 下」(百田尚樹著/幻冬舎文庫)
から引用していきます。
「南京大虐殺」とは、支那事変以降、アメリカで蒋介石政権が盛んに
行なった反日宣伝活動のフェイクニュースでした。日本軍による「残
虐行為」 があったとアメリカのキリスト教団体とコミンテルンの工作
員が盛んに宣伝し、「残虐な日本軍と犠牲者・中国」というイメージ
を全米に広めたのです。 このイメージに基づいて、後年、第二次世界
大戦後に開かれた「極東国際軍事裁判」(東京裁判)では、日本軍の悪
行を糾弾する材料として「南京大虐殺」が取り上げられることになり
ます。
実は東京裁判でもおかしなことがありました。 この裁判では、 上官
の命令によって一人の捕虜を殺害しただけで絞首刑にされたBC級戦犯
が千人もいたのに、三十万人も殺したはずの南京大虐殺では、南京司
令官の松井石根大将一人しか罪に問われていないのです。規模の大きさ
からすれば、本来は虐殺命令を下した大隊長以下、中隊長、小隊長、
さらに直接手を下した下士官や兵などが徹底的に調べ上げられ、何千
人も処刑されているはずです。 しかし現実には、処刑されたのは松井
大将一人だけでした。
東京裁判で亡霊の如く浮かび上がった 「南京大虐殺」は、それ以降、
再び歴史の中に消えてしまいます。 「南京大虐殺」が再び姿を現すの
は、東京裁判の四半世紀後のことでした。
昭和四六年(一九七一)、朝日新聞のスター記者だった本多勝一(かつ
いち)が「中国の「旅」という連載を開始しました。その中で本多は、
「南京大虐殺」を取り上げ、日本人がいかに残虐なことをしてきたかを、
嘘とデタラメを交えて書いたのです。これが再燃のきっかけとなりまし
た。この時の取材、 本多の南京滞在はわずか一泊二日、「南京大虐殺」
を語った証言者は中国共産党が用意したわずか四人でした。後に本多自
身が「「中国の視点」を紹介することが目的の「旅」であり、その意味
では「取材」でさえもない」と語っています。
本多の連載が始まった途端、朝日新聞をはじめとする日本の多くのジャ
ーナリズムが「南京大虐殺」をテーマにして「日本人の罪」 を糾弾する
記事や特集を組み始めました。そうした日本国内での動きを見た中国政
府は、これは外交カードに使えると判断したのでしょう。以降、執拗に
日本政府を非難するようになったというわけです。 本多勝一の記事が
出るまで、毛沢東も周恩来も中国政府も、一度たりとも公式の場で言及
したことはなく、日本を非難しなかったにもかかわらずです。それ以前
は、中国の歴史教科書にも「南京大虐殺」は書かれていませんでした。
「なかったこと」を証明するのは、俗に「悪魔の証明」といわれ、ほぼ
不可能なこととされています。つまり、私がここで書いたことも、「な
かったこと」の証明にはなりません。ただ、客観的に見れば、組織的お
よび計画的な住民虐殺という意味での「『南京大虐殺」はなかった」と考
えるのがきわめて自然です。
(198〜200p)
私が若い時に、憧れた人物は2人。
アラビアのロレンスと本田勝一さんでした。
話題になっている「中国の旅」は読みました。老婆の写真が載った表紙は
今でも脳裏に焼き付いています。
現場に行って、話を聞いてルポを書く手法は、
素晴らしいなと思い、教員としても、現場主義を心掛けてきました。
鍛冶屋を教えるのに、実際に行って見て、聞いているのも、
その現場主義を心掛けているからです。
南京大虐殺のきっかけは、「中国の旅」であり、
それが不正確かも知れないという内容はドキドキします。
何が正しいんだ。
本田勝一さんの意見が聞きたい。
※参考:(下)朝日記事「万人坑」はなかったという指摘に本多勝一氏はこう返答した…「中国の主張を代弁しただけ」
「支那事変」は確固たる目的がないままに行なわれた戦争でした。
乱暴な言い方をすれば、中国人の度重なるテロ行為に、お灸をすえて
やるという世論に押される形で戦闘行為に入ったものの、気が付けば
全面的な戦いになっていたという計画性も戦略もない愚かなものでし
た。
名称だけは「事変」となっていましたが、もはや完全な戦争でした。
しかもこの戦いは現地の軍の主導で行なわれ、政府がそれを止めるこ
とができないでいるという異常なものでもありました。そこには五・
一五事件や二・二六事件の影響があるのは明らかです。
支那事変が始まった翌年の昭和一三年(一九三八)には、「国家総動員
法」が成立しました。これは「戦時に際して、労働力や物資割り当て
などの統制・運用を、議会の審議を経ずに勅令で行なうことができる
ようにした法律」です。具体的には、国家は国民を自由に徴用でき、
あらゆる物資や価格を統制し、言論を制限しうるといった恐るべき法
律でした。ちなみにこの法案の審議中、趣旨説明をした佐藤賢了(け
んりょう)陸軍中佐のあまりに長い答弁に、衆議院議員たちから抗議
の声が上がったところで、佐藤が「黙れ!」と一喝したことがありまし
た。このとき議員たちの脳裏に二年前の二・二六事件が浮かんだこと
は容易に想像できます。佐藤の恫喝後、誰も異議を挟まなくなり、狂
気の法案はわずか一ヵ月で成立しました。
国力のすべてを中国との戦争に注ぎ込もうと考えていた日本はこの年、
二年後に東京で開催予定であった「オリンピック」と「万国博覧会」
(万博) を返上します。 これは、もはや世界の国々と仲良く手を結ん
でいこうという意思がないことを内外に宣言したに等しい決断でした。
このオリンピックと万博の返上は陸軍の強い希望であったといわれて
います。
(203〜204p)
二・二六事件の影響の話。
国会で「黙れ!」と言った陸軍中佐。
軍部に力が、国会を上回った証明みたいです。
反対できない議員。
命は惜しいですからね。
同じ昭和一三年(一九三八)、ヨーロッパではドイツがオーストリアを
併合し、チェコスロバキアのズデーテン地方を要求する事態となって
いました。チェコは拒否しますが、ヒトラーは戦争をしてでも奪うと
宣言します。 イギリスとフランスの首相がヒトラーと会談しましたが
(ミュンヘン会談)、英仏両国は、チェコを犠牲にすれば戦争は回避で
きると考え、ヒトラーの要求を全面的に受け入れます。そのためにチ
ェコは自国領土の一部をむざむざとドイツに奪われました。
イギリスとフランスが取った「宥和(ゆうわ)政策」は当時、ヨーロ
ッパの平和を維持するための現実的で勇気ある判断として大いに評価
され、ミュンヘン会談を終えてロンドン郊外のクロイドン空港に降り
立ったチェンバレン首相を、イギリス国民は大歓迎しました。
しかしこの「宥和政策」は、結果的にドイツに時間的、資金的な猶予
を与えただけのものとなりました。結果論ではありますが、この時、
イギリスとフランスが軍備を拡充して敢然とヒトラーに対峙していた
ならば、第二次世界大戦は避けられたかもしれません。仮に戦争にな
ったとしても、全ヨーロッパが火の海となり、夥しい死者が出る悲惨
な状況にはならなかったと思われます。 狂気の独裁者に対して宥和政
策を取るということは、一見、危険を回避したように見えますが、よ
り大きな危険を招くことにもつながるという一種の教訓です。
(205p)
この教訓は今に生きています。
プーチンに妥協しないことです。
歴史から学ぶべきです。


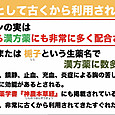










コメント