「ペリリュー・沖縄戦記」② 頭上を砲弾が飛んできて爆発する戦場
今日は令和4年7月12日。
前記事に引き続き、
「ペリリュー・沖縄戦記」(ユージン・B・スレッジ著
伊藤真/曽田和子訳 講談社学術文庫)より。
しかしあの戦いのさなか、海兵隊員たちは間違いなく、心の底から、
激しく日本兵を憎んでいた。こうした憎悪を否定したり軽視したり
するなら、私が太平洋の戦場で生死を共にした海兵隊員たちの固い
団結心や熱烈な愛国心を否定するのと同じぐらい、真っ赤な嘘をつ
いていることになるだろう。
日本兵もまた、われわれアメリカ兵に対して同様の憎悪を抱いてい
たに違いない。ペリリュー島と沖縄での戦場体験を通じて、私はそ
う確信した。彼らは狂信的な敵愾心(てきがいしん)を抱いていた。
つまり、日本兵たちは、戦後の多くのアメリカ人にはーーーひょっ
として現代の多くの日本人でさえーーーほとんど理解できないほど
強烈に、自分たちの大義を信じていたのだ。
海兵隊員の日本兵に対する憎悪と、日本兵の大義に寄せる火の玉の
ような熱い思いは、両者のあいだに容赦のない、残忍かつ凶暴な戦
闘をもたらした。それは、太平洋を舞台にした戦争特有の、理性の
かけらもない、原始的な憎しみのぶつかり合いだった。このような
殺し合いは世界に類がない。戦場の部隊がどのようなことに耐え抜
いたかを理解するためには、海兵隊が戦った戦争のこうした様相を
十分に考慮しなければならない。
(59~60p)
容赦のない、残忍かつ凶暴な戦闘。
これを体験した著者が、日本人がアメリカ兵を憎んでいたこと、
大義を信じていたことを肌で感じたのでしょう。
火炎放射器の話。
まるで家の庭にホースで水を撒くように簡単に、地獄の炎のような
火炎を自由に噴射できるのだーーーそう思うとうまく標的に命中さ
せた興奮もさめてしまった。敵を銃弾や砲弾の破片で殺害するのは、
残酷ではあるが、戦争では避けることができない現実だ。しかし相
手をこうして焼き殺すというのは、考えただけでも身の毛もよだつ
恐ろしい行為だった。それでものちに私は、この火炎放射器なしに
は日本兵を島の陣地から一掃することはできないという事実を、思
い知らされることになった。
(62p)
ペリリューでの戦いの記述で、火炎放射器でトーチカに潜む
日本人を焼き殺すシーンがありました。
恐怖だっただろうなと思いました。
「今のはこっちのですかね、それとも敵の?」砲弾が頭上を飛ぶた
びに私はスナフに訊いた。
砲弾が飛んできて、爆発するーーーそこには情け容赦もない。遠く
から空を切って接近してくるのが聞こえるだけで、全身の筋肉が硬
くこわばった。恐怖に押し流されまいとして、なんとかふんばって
みる。そんなとき私は、どうしようもない無力感に襲われた。
砲弾の甲高い咆哮がいよいよ間近に迫ると、私は歯をぎりぎり言わ
せて食いしばった。動悸がし、口が渇き、自然と目が細くなる。全
身を汗が流れ、呼吸は乱れて短い喘(あえ)ぎに変わり、息が詰ま
るのを恐れてつばも飲み込めない。あとは祈ることしかできなかっ
た。
(115p)
砲弾が頭上を飛びかうなんて、想像もしたくない状況です。
こんな気持ちになるのだと、伝わってきました。
だが突然、日本軍の機銃弾が頭上を襲った。これほどの狭い範囲に
これほどの猛烈な機銃掃射が加えられるのは見たことがなかった。
曳光弾の閃光が走り、われわれが迫撃砲を設置した窪地の上、30
センチもないあたりで銃弾がはじける。われわれは地面に仰向けに
横たわったまま、機関銃の連射音がやむのを待った。
ふたたび機関銃が火を噴き、そこへ第二の機関銃が加わる。三人目
もいたかもしれない。青白い曳光弾の光が何本も頭上を流れていく
(わが軍は曳光弾は赤かった)。飛行場のあたりから撃っているら
しい。敵の十字砲火は少なくとも15分は続いた。まさに猛射とい
うにふさわしかった。
(118p)
これもすごい体験です。
仰向けに寝た上を機関銃の銃弾が流れていったのです。
曳光弾の色が、日本とアメリカでは違ったことを知りました。
つづく


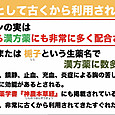










コメント