本「デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士」③ 家族の中で唯一のろう者の苦しみ
今日は令和6年1月18日。
前記事に引き続き、
「デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士」
(丸山正樹著/文春文庫)より引用します。
そんな彼らを見ていて、再びあの感情が蘇る。
兄たち家族とて、この手のレストランに来るのが初めてということは
ないだろう。その際にも、今のように意思の疎通に不自由を感じる場
面はあっただろうが、自分たちだけで何とか切り抜けたはずだ。
だが、自分がいると「聴こえるろう者」である荒井がいると、何のた
めらいもなく彼らは自分に頼る。通訳をさせ、交渉事を任す。
親とて、そうだった。
荒井は、幼いころから嫌というほど 「家族と世間」との間の「通訳」
をしてきたのだった。 買い物や遊びに行った先で。 学校の親子面談
では教師と親の間に入って。 銀行や役所に連れて行かれたこともた
びたびあった。
だが、一番つらかったのは、と思い出す。
母と一緒に病院へ、父の検査の結果を聞きに行った時だった。最初は
筆談でそれを母に伝えようとしていた医師だったが、走り書きの悪筆
を母がなかなか読めず、 結局荒井が医師の言葉を母に伝えることにな
ったのだ。
荒井ははっきりと覚えている。 医師が困ったように、だが、仕方がな
い、という顔で口にしたその言葉を。
お父さんは、末期の肺ガンです。 もって半年。おそらく今年いっぱい
もたないと思います。
荒井は、それを母に伝えた。母は、信じられないという顔で、医師に
もう一度確かめるようにと言った。そしてそれが本当のことだと悟ると、
顔を覆ってその場で泣きだした。
荒井は泣けなかった。
しっかりしなければ。自分がしっかりしなければ、とそれだけを思っ
ていた。彼はまだその時、十一歳。今の司とほとんど同じ年だったの
だ。
(97〜98p)
まだ小学生なのに、家族のために「家族と世間」の通訳をしなくては
ならない立場。
そして父親の末期ガンを伝えなくてはならなかった体験。
今まで知らなかった立場の人です。
その時、 「ママ、 あっち、あっち」とはしゃいだ声とともに、荒井た
ちのテーブルの脇を三、四歳の子どもが駆け抜けて行った。
そんなに走ったら危ないぞ、と思わず目で追う。
案の定、子どもが転倒した。今までの元気はどこへやら、火がついた
ように泣きだす。すぐに母親らしき女性が駆け寄って抱き起こしたが、
子どもはなかなか泣きやまない。そんな子どもを、母親は懸命にあや
している。
その光景をぼんやりと眺めていた荒井の脳裏に、幼いころの記憶が蘇
った。
今の子どもと同じぐらいの年齢ではなかったか。道を走っていて、思
い切り転倒したことがあった。前を歩く母親に駆け寄ろうとしていた
のかもしれない。とにかく母親がすぐ前を歩いていたことは確かだ。
荒井は、泣いて、母親を呼んだ。だが母親は、振り向きも、立ち止ま
りもしなかった。荒井はさらに大声で泣き喚いた。それでも母親は気
づかず、歩いて行くだけだった。
ああ、お母さんは聴こえないんだ。
遠ざかっていく後ろ姿を見ながら、 荒井はそのことを思い知った。
同時に、学びもした。転んで泣いても、誰も助けてはくれないのだと。
それから彼は、転んでも泣かない子になった。
泣いて助けを求めても、その声は誰にも届かない。ただ我慢するしか
ないのだ。そして、立ち上がり、自分で歩きだすしかないのだ。
(102〜103p)
これも想像できない、想像したことがない状況だと思います。
大声で泣いても無駄であることを知った子どもは、
「自分で歩き出すしかない」と思うだろうな。
片貝のピッチは、さらに上がっていった。それにつれ、彼の手話も
饒舌になっていく。
荒井は、もっぱら聞き役に徹することにした。
〈私は〉〈三歳の時にかかったはしかが原因で〉 〈聴こえなくなっ
たんです〉
酔うにつれ、片貝は自分のことを語り始めた。
〈両親は〉〈私に〉〈あらゆる治療を試した〉 〈でも〉 〈治らな
いと悟ると〉〈今度は〉〈何とか近づけようとした〉 〈「聴こえ
る子」に〉
グラスに残ったビールを一気にあおり、再び手を動かす。
〈補聴器〉〈人工内耳〉 〈聴覚口話法〉 〈インテグレーション〉
次々と単語が出てくる。
<ご存知ですよね?〉
荒井は肯いた。人工内耳とは、内耳に電極などを埋め込み、直接
聴覚神経を刺激することで聴こえを補助するもので、中途失聴者、
特に子どものうちに手術をすればかなりの効果があると言われて
いる。
インテグレーションとは「統合教育」の意味で、ろう児がろう学
校に通わないで、地域の普通学校で学ぶことをいう。三十年ほど
前から盛んになった教育法で、片貝などはインテグレーションを
受けた最初の世代になるのかもしれない。
〈ろう学校で〉〈私の聴覚口話法の成績は〉〈トップクラスでし
た〉 〈でも〉〈普通学校にインテグレートした後は〉〈想像が
つくでしょう?〉
荒井が肯くのを見て、片貝は続ける。
〈いくら〉〈ろう者社会の中では〉 〈「話すのが上手」でも〉
〈聴者社会にあっては> <「変なしゃべり方をする子」でしかな
い〉〈特に子どもは正直だから〉
片貝はそこで寂しげな笑みを浮かべた。
〈それからです〉〈本気で〉〈死に物狂いで〉 〈勉強を始めたの
は〉〈負けたくなかった〉 〈聴者の子どもたちに〉〈日常の会話
では〉〈敵わなくても〉 〈机上の勉強では〉〈彼らに追いつき〉
〈追い抜くことができる〉〈いや〉〈絶対に追い抜いてみせる〉
少し目をすがめるようにしてから、再び続ける。
〈テストで一番をとった時〉〈両親はもちろん喜んでくれました〉
〈でも〉〈私には分かった〉 〈両親にとって一番嬉しいのは〉
〈私が成績優秀になることではなく〉〈「普通の子」になること〉
〈「聴こえる子」になってくれることだった〉
〈両親がありのままの私を受け入れてくれることは〉〈ついにあ
りませんでした〉 〈両親が手話を覚えることも〉〈なかった〉
〈私たちは〉〈結局一度も〉〈まともに会話したことさえなかっ
たんです〉〈私は常に〉〈「損なわれた子」だったんです〉
間断なく動いていた片貝の手が、ふいに止まった。
(107〜108p)
ドラマでこの片貝役の人の演技に注目したいです。
この場面、家族の中で唯一ろう者の立場の苦しみが、
酔った勢いで感情的に表現されることでしょう。
どんな手話なのか、どんな表情なのか。

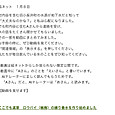











コメント